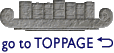知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました
争点別に注目判決を整理したもの
実質上拡張変更
実質上拡張変更 ┃ 2024年 ┃ 2022年 ┃ 2021年 ┃ 2020年 ┃ 2019年 ┃ 2017年 ┃ 2016年 ┃ 2015年 ┃ 2012年 ┃ 2011年 ┃ 2009年 ┃ 2007年 ┃ 2004年 ┃ 2003年 ┃ 2002年┃
2019.08. 2
平成30(行ケ)10133 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 令和元年7月18日 知的財産高等裁判所
訂正審判において、訂正事項が実質上特許請求の範囲を変更すると判断されました。知財高裁もこれを維持しました。
(2) 訂正事項2が実質上特許請求の範囲を変更するものであるか否かについ て
ア 訂正をすべき旨の審決が確定したときは,訂正の効果は出願時に遡って 生じ(特許法128条),訂正された特許請求の範囲の記載に基づいて技 術的範囲が定められる特許発明の特許権の効力は第三者に及ぶことに鑑み ると,同法126条6項の「実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更す るもの」であるか否かの判断は,訂正の前後の特許請求の範囲の記載を基 準としてされるべきであり,「実質上」の拡張又は変更に当たるかどうか は訂正により第三者に不測の不利益を与えることになるかどうかの観点か ら決するのが相当である。 また,特許請求の範囲の記載に関し,同法36条5項前段は,特許請求 の範囲には,請求項に区分して,各請求項ごとに特許出願人が特許を受け ようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなけ ればならないと規定している。この規定の趣旨は,一つの請求項から発明 が把握されるようにするため,各請求項ごとに特許出願人自らが「特許を 受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」と判断 した事項を特許請求の範囲に記載することを求めたものと解されるから, 客観的にみると,一つの請求項に内容的に重複する記載がある場合であっ ても,相互に矛盾するものでなければ,特許出願人自らが「特許を受けよ うとする発明を特定するために必要と認める事項」と判断したものとして 解釈するのが相当である。
以上を前提に,訂正事項2が実質上特許請求の範囲を変更するものであ るか否かについて判断する。
イ 本件訂正前の請求項1のただし書の「ただし,R1 及びR2 が同時に水素 原子であることはない。」との文言は,その文理上,R1 及びR2 の両方が 水素原子でないことを特定するにとどまり,R1 又はR2 のいずれか一方が 必ず水素原子であることまで特定したものと理解することはできない。 しかるところ,本件訂正前の請求項1の記載全体をみると,「R1はフッ 素であり」及び「R2は塩素であり」との記載があり,この記載は,「R1」 を「フッ素」に,「R2」を「塩素」にそれぞれ特定したものであることは 明らかである。そして,この記載は,R1 及びR2 の両方が水素原子でない ことをも意味するものと理解できるから,その点においては,ただし書の 記載と重複する内容を含むものであるが,相互に矛盾するものではない。 また,本件明細書の「前記化学式1において,…R1 及びR2 は各々水素 原子,C1−C6アルコキシ,C1−C6アルキルまたはハロゲンであり,…前 記ハロゲンはフッ素,塩素,臭素またはヨー素を意味する。」(【000 9】)及び「本発明による前記化学式1で表される化合物において,特に\n好ましくは,…R1 及びR2 は水素原子,F,Cl,メチルまたはメトキシ であり」(【0010】)との記載中には,化学式1のR1 及びR2 の例と してF(フッ素)及びCl(塩素)が開示されているから,本件訂正前の 請求項1において「R1」を「フッ素」に,「R2」を「塩素」に特定する ことは,本件明細書の記載との関係においても整合するものである。 そうすると,ただし書の記載と「R1 はフッ素であり」及び「R2 は塩素 であり」との記載は,「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定す るために必要と認める事項」であると理解できるものであり,本件訂正前 の請求項1におけるR1 及びR2 の定義が不明瞭であるということはできな い。 このように訂正事項2は,本件訂正前の請求項1記載の「R2」の「塩素」 を「水素」に訂正するものであるから,特許請求の範囲を変更するもので ある。また,本件訂正前の請求項1の「R1 はフッ素であり」及び「R2 は 塩素であり」との記載文言から,R1 は「フッ素又は水素」を,R2 は「フ ッ素又は水素」を実質的に意味するものと理解することはできないから, 訂正事項2による特許請求の範囲の変更は,減縮的な変更には当たらない。 そして,訂正事項2により,請求項1に係る発明は,本件訂正前の請求 項1に記載される化合物1の置換基である「R2」が塩素である化合物群か ら訂正後の「R2」が水素である化合物群に変更されることになるから,こ の変更により,本件訂正前の請求項1の記載の表示を信頼した第三者に不\n測の不利益を与えることになることは明らかである。 したがって,訂正事項2は,実質上特許請求の範囲を変更するものと認 められるから,特許法126条6項の要件に適合しないというべきである。 これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
(3) 原告らの主張について
原告らは,本件訂正前の請求項1の記載及び本件明細書の記載を考慮し, また,本件特許の出願経過を参酌すれば,本件訂正前の請求項1の本文の 「R 1 はフッ素であり,R2 は塩素であり」との記載は,ただし書の「R1 及 びR2が同時に水素原子であることはない。」との関係が不明瞭であり,実質 的に,本文のR1 及びR2 の範囲は,塩素だけではなく水素を含むはずである と理解され,訂正事項2は,実質的に理解されるR2の範囲から塩素を削除す ることによりR2の範囲を限定するものであるから,実質上特許請求の範囲を 変更する訂正ではない旨主張する。 しかしながら,前記(2)イのとおり,本件訂正前の請求項1の特許請求の範 囲の記載によれば,本件訂正前の請求項1の本文の「R1はフッ素であり」及 び「R2は塩素であり」との記載は,「R1」を「フッ素」に,「R2」を「塩 素」にそれぞれ特定したものであることは明らかであり,ただし書の「R1 及びR 2 が同時に水素原子であることはない。」との記載と重複する内容を 含むものであるが,相互に矛盾するものではなく,本件明細書の記載との関 係においても整合するものであるから,本文の記載とただし書の記載が不明 瞭であるということはできない。 次に,本件特許の出願経過によれば,本件訂正前(本件特許の設定登録時) の請求項1は,本件拒絶査定不服審判の請求とともにされた第2次補正によ り第1次補正後の請求項1が補正されたものであるが,本件拒絶査定不服審 判の審判請求書(乙3)には,「3.2.上記補正は,請求項1において, R1 をフッ素に限定し,R2 を塩素に限定し(特許請求の範囲の限定的減縮に あたります),…適正な補正です。」,「3.3.上記補正により,本願発 明の化合物は,本願明細書の表2に記載される薬理試験結果において,当業\n者が予測し得ない程度の優れた抗腫瘍活性を奏するもの及びこれらと同視さ\nれる化合物に限定され,審査官殿が指摘された,「引用文献3の化合物42 と同程度の活性又は劣る活性を示す化合物(例えば化合物52,73,11 5,136,157,193など)」は明確に排除されています。」との記 載があり,この記載から,上記補正は,請求項1におけるR1をフッ素に限定 し,R2を塩素に限定するものであることを明確に理解できる。そして,本件 明細書記載の化合物52,73にはR2に水素が,化合物115,136,1 57にはR1に水素が含まれており,本件拒絶査定不服審判の審判請求書の上 記記載は,本件明細書の記載とも整合することからすると,本件訂正前の請 求項1におけるR1及びR2の定義が不明瞭であるということはできない。 また,本件拒絶査定(甲16)には,「本願発明の化合物10は,引用文 献3の化合物42に比して優れた抗腫瘍活性を示すものと認められる」との 記載があるが,この記載は,原告らが述べるような審査官が化合物10を特 許請求の範囲の記載に包含させなくてはならないことを意図して記載したも のとはいえないし,特許請求の範囲の記載は特許許出願人自らが「特許を受 けようとする発明を特定するために必要と認める事項」を記載すべきもので あり(特許法36条5項),原告らは,自らの責任で特許請求の範囲の記載 を選択すべきであることからすると,本件拒絶査定の上記記載を参酌するこ とにより,本件訂正前の請求項1におけるR1 及びR2 の定義が不明瞭である ということはできない。
さらに,原告らは,本件特許の出願経過として参酌されるべき事情として, 第2次補正における「R2は塩素であり,」との記載は,審査官と原告らの代 理人の小川弁理士の補正に関する合意の内容と整合しないことを指摘するが, 原告ら主張の合意は,第三者との関係からすれば,出願経過における願書, 願書に添付した明細書,特許請求の範囲,図面等の審査に係る書類,拒絶査 定不服審判に係る書類等の手続書類と同列に扱うことはできず,本件訂正前 の請求項1の解釈において参酌することはできない。 したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。
(2) 訂正事項2が実質上特許請求の範囲を変更するものであるか否かについ て
ア 訂正をすべき旨の審決が確定したときは,訂正の効果は出願時に遡って 生じ(特許法128条),訂正された特許請求の範囲の記載に基づいて技 術的範囲が定められる特許発明の特許権の効力は第三者に及ぶことに鑑み ると,同法126条6項の「実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更す るもの」であるか否かの判断は,訂正の前後の特許請求の範囲の記載を基 準としてされるべきであり,「実質上」の拡張又は変更に当たるかどうか は訂正により第三者に不測の不利益を与えることになるかどうかの観点か ら決するのが相当である。 また,特許請求の範囲の記載に関し,同法36条5項前段は,特許請求 の範囲には,請求項に区分して,各請求項ごとに特許出願人が特許を受け ようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなけ ればならないと規定している。この規定の趣旨は,一つの請求項から発明 が把握されるようにするため,各請求項ごとに特許出願人自らが「特許を 受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」と判断 した事項を特許請求の範囲に記載することを求めたものと解されるから, 客観的にみると,一つの請求項に内容的に重複する記載がある場合であっ ても,相互に矛盾するものでなければ,特許出願人自らが「特許を受けよ うとする発明を特定するために必要と認める事項」と判断したものとして 解釈するのが相当である。
以上を前提に,訂正事項2が実質上特許請求の範囲を変更するものであ るか否かについて判断する。
イ 本件訂正前の請求項1のただし書の「ただし,R1 及びR2 が同時に水素 原子であることはない。」との文言は,その文理上,R1 及びR2 の両方が 水素原子でないことを特定するにとどまり,R1 又はR2 のいずれか一方が 必ず水素原子であることまで特定したものと理解することはできない。 しかるところ,本件訂正前の請求項1の記載全体をみると,「R1はフッ 素であり」及び「R2は塩素であり」との記載があり,この記載は,「R1」 を「フッ素」に,「R2」を「塩素」にそれぞれ特定したものであることは 明らかである。そして,この記載は,R1 及びR2 の両方が水素原子でない ことをも意味するものと理解できるから,その点においては,ただし書の 記載と重複する内容を含むものであるが,相互に矛盾するものではない。 また,本件明細書の「前記化学式1において,…R1 及びR2 は各々水素 原子,C1−C6アルコキシ,C1−C6アルキルまたはハロゲンであり,…前 記ハロゲンはフッ素,塩素,臭素またはヨー素を意味する。」(【000 9】)及び「本発明による前記化学式1で表される化合物において,特に\n好ましくは,…R1 及びR2 は水素原子,F,Cl,メチルまたはメトキシ であり」(【0010】)との記載中には,化学式1のR1 及びR2 の例と してF(フッ素)及びCl(塩素)が開示されているから,本件訂正前の 請求項1において「R1」を「フッ素」に,「R2」を「塩素」に特定する ことは,本件明細書の記載との関係においても整合するものである。 そうすると,ただし書の記載と「R1 はフッ素であり」及び「R2 は塩素 であり」との記載は,「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定す るために必要と認める事項」であると理解できるものであり,本件訂正前 の請求項1におけるR1 及びR2 の定義が不明瞭であるということはできな い。 このように訂正事項2は,本件訂正前の請求項1記載の「R2」の「塩素」 を「水素」に訂正するものであるから,特許請求の範囲を変更するもので ある。また,本件訂正前の請求項1の「R1 はフッ素であり」及び「R2 は 塩素であり」との記載文言から,R1 は「フッ素又は水素」を,R2 は「フ ッ素又は水素」を実質的に意味するものと理解することはできないから, 訂正事項2による特許請求の範囲の変更は,減縮的な変更には当たらない。 そして,訂正事項2により,請求項1に係る発明は,本件訂正前の請求 項1に記載される化合物1の置換基である「R2」が塩素である化合物群か ら訂正後の「R2」が水素である化合物群に変更されることになるから,こ の変更により,本件訂正前の請求項1の記載の表示を信頼した第三者に不\n測の不利益を与えることになることは明らかである。 したがって,訂正事項2は,実質上特許請求の範囲を変更するものと認 められるから,特許法126条6項の要件に適合しないというべきである。 これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。
(3) 原告らの主張について
原告らは,本件訂正前の請求項1の記載及び本件明細書の記載を考慮し, また,本件特許の出願経過を参酌すれば,本件訂正前の請求項1の本文の 「R 1 はフッ素であり,R2 は塩素であり」との記載は,ただし書の「R1 及 びR2が同時に水素原子であることはない。」との関係が不明瞭であり,実質 的に,本文のR1 及びR2 の範囲は,塩素だけではなく水素を含むはずである と理解され,訂正事項2は,実質的に理解されるR2の範囲から塩素を削除す ることによりR2の範囲を限定するものであるから,実質上特許請求の範囲を 変更する訂正ではない旨主張する。 しかしながら,前記(2)イのとおり,本件訂正前の請求項1の特許請求の範 囲の記載によれば,本件訂正前の請求項1の本文の「R1はフッ素であり」及 び「R2は塩素であり」との記載は,「R1」を「フッ素」に,「R2」を「塩 素」にそれぞれ特定したものであることは明らかであり,ただし書の「R1 及びR 2 が同時に水素原子であることはない。」との記載と重複する内容を 含むものであるが,相互に矛盾するものではなく,本件明細書の記載との関 係においても整合するものであるから,本文の記載とただし書の記載が不明 瞭であるということはできない。 次に,本件特許の出願経過によれば,本件訂正前(本件特許の設定登録時) の請求項1は,本件拒絶査定不服審判の請求とともにされた第2次補正によ り第1次補正後の請求項1が補正されたものであるが,本件拒絶査定不服審 判の審判請求書(乙3)には,「3.2.上記補正は,請求項1において, R1 をフッ素に限定し,R2 を塩素に限定し(特許請求の範囲の限定的減縮に あたります),…適正な補正です。」,「3.3.上記補正により,本願発 明の化合物は,本願明細書の表2に記載される薬理試験結果において,当業\n者が予測し得ない程度の優れた抗腫瘍活性を奏するもの及びこれらと同視さ\nれる化合物に限定され,審査官殿が指摘された,「引用文献3の化合物42 と同程度の活性又は劣る活性を示す化合物(例えば化合物52,73,11 5,136,157,193など)」は明確に排除されています。」との記 載があり,この記載から,上記補正は,請求項1におけるR1をフッ素に限定 し,R2を塩素に限定するものであることを明確に理解できる。そして,本件 明細書記載の化合物52,73にはR2に水素が,化合物115,136,1 57にはR1に水素が含まれており,本件拒絶査定不服審判の審判請求書の上 記記載は,本件明細書の記載とも整合することからすると,本件訂正前の請 求項1におけるR1及びR2の定義が不明瞭であるということはできない。 また,本件拒絶査定(甲16)には,「本願発明の化合物10は,引用文 献3の化合物42に比して優れた抗腫瘍活性を示すものと認められる」との 記載があるが,この記載は,原告らが述べるような審査官が化合物10を特 許請求の範囲の記載に包含させなくてはならないことを意図して記載したも のとはいえないし,特許請求の範囲の記載は特許許出願人自らが「特許を受 けようとする発明を特定するために必要と認める事項」を記載すべきもので あり(特許法36条5項),原告らは,自らの責任で特許請求の範囲の記載 を選択すべきであることからすると,本件拒絶査定の上記記載を参酌するこ とにより,本件訂正前の請求項1におけるR1 及びR2 の定義が不明瞭である ということはできない。
さらに,原告らは,本件特許の出願経過として参酌されるべき事情として, 第2次補正における「R2は塩素であり,」との記載は,審査官と原告らの代 理人の小川弁理士の補正に関する合意の内容と整合しないことを指摘するが, 原告ら主張の合意は,第三者との関係からすれば,出願経過における願書, 願書に添付した明細書,特許請求の範囲,図面等の審査に係る書類,拒絶査 定不服審判に係る書類等の手続書類と同列に扱うことはできず,本件訂正前 の請求項1の解釈において参酌することはできない。 したがって,原告らの上記主張は,採用することができない。