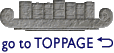知財みちしるべ:最高裁の知的財産裁判例集をチェックし、判例を集めてみました
争点別に注目判決を整理したもの
不正競争(その他)
不正競争(その他) ┃ 2025年 ┃ 2024年 ┃ 2023年 ┃ 2022年 ┃ 2021年 ┃ 2020年 ┃ 2019年 ┃ 2017年 ┃ 2016年 ┃ 2015年 ┃ 2014年 ┃ 2013年 ┃ 2012年 ┃ 2010年 ┃ 2009年 ┃ 2007年 ┃ 2006年 ┃ 2005年 ┃ 2004年┃
2025.02. 2
令和5(ワ)70022 商標権侵害行為等差止請求事件 商標権 民事訴訟 令和7年1月14日 東京地方裁判所
一部の請求について、日本の裁判所が管轄権を有しないと判断されました。
(1) 事案に鑑み、民訴法3条の3第5号に基づく国際裁判管轄の有無に先立ち、 同第8号に基づく国際裁判管轄の有無について検討する。
ア 不法行為に基づく損害賠償請求訴訟につき、民訴法3条の3第8号の規 定に依拠して我が国の国際裁判管轄を肯定するためには、原則として、被 告が日本国内でした行為により原告の権利利益について損害が生じたか、 被告がした行為により原告の権利利益について日本国内で損害が生じたと の客観的事実関係が証明されれば足りると解するのが相当である(最高裁 平成12年(オ)第929号、同年(受)第780号同13年6月8日第 二小法廷判決・民集55巻4号727頁及び最高裁平成23年(受)第1 781号同26年4月24日第一小法廷判決・民集68巻4号329頁参 照)。
イ 民訴法3条の3第8号の「不法行為に関する訴え」は、違法行為により 権利利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者が提起する差止請求 に関する訴えをも含むものと解される。そして、このような差止請求に関 する訴えについては、違法行為により権利利益を侵害されるおそれがある にすぎない者も提起することができる以上は、同号の「不法行為があった 地」は、違法行為が行われるおそれのある地や、権利利益を侵害されるお それのある地をも含むものと解するのが相当である。 違法行為により権利利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者が提起する差止請求に関する訴えの場合において、同号の「不法行為があっ た地」が日本国内にあるというためには、被告が原告の権利利益を侵害す る行為を日本国内で行うおそれがあるか、原告の権利利益が日本国内で侵 害されるおそれがあるとの客観的事実関係が証明されれば足りるというべ きである(前記最高裁平成26年4月24日判決参照)。
ウ 以上を踏まえ、本件各請求に係る訴えについて、民訴法3条の3第8号 に基づき、日本の裁判所が管轄権を有するか否かを検討する。
(2) 本件請求1から4まで、6の1及び6の2に係る訴えについて
ア 原告は、被告が、本件被告ウェブサイトにおいて、契約書レビューサー ビスの提供に関する広告及び価格表に被告標章を付して電磁的方法により\n提供すること(本件請求1、2及び6の1)、契約書レビューサービスの提 供に被告表示を使用すること(本件請求3、4及び6の2)により、原告\nの権利利益が日本国内で侵害され、又は侵害されるおそれがあるとの客観 的事実関係が証明されている旨及び原告の権利利益について日本国内で損 害が生じたとの客観的事実関係が証明されている旨を主張する。
イ 前記前提事実(2)ウによれば、被告は、本件被告ウェブサイト上の「AI に基づく契約書及び電子メールアカウントのレビュー」についての広告及 び価格表に被告標章(被告表\示)を表示していたことが認められるところ、\n本件被告ウェブサイトは日本においても閲覧することができたものである (弁論の全趣旨)。 しかしながら、被告が、本件被告ウェブサイトにおける「AIに基づく 契約書及び電子メールアカウントのレビュー」について、日本国内の利用 者にサービスを提供していることを示す証拠は見当たらないところ、証拠 (甲2、8、乙1)によれば、1)本件被告ウェブサイトは全て英語で記載 されていること、2)本件被告ウェブサイトに掲載された価格表には、米国\nドルでの価格が表示されており、円での価格は表\示されていないこと、3) 本件被告ウェブサイトには、被告に対する問合せ先として、メールアドレ ス((メールアドレス省略))とともに米国の住所及び電話番号が記載されており、日本の住所又は電話番号は記載されていないこと、4)本件被告ウェブサイトには、日本語で作 成された契約書又は日本法を準拠法とする契約書に関するレビューサービ スについての記載はないこと、5)本件被告ウェブサイトのサーバは米国に 所在すること、6)被告は、「LegalForce」の文字を含む標章を付 した役務の提供を日本において申し出る計画を有していないことが認めら\nれる。以上の点を考慮すれば、本件被告ウェブサイトを日本において閲覧 することができたことを踏まえても、本件被告ウェブサイトにおける被告 標章(被告表示)の表\示が、日本の需要者を対象としたものであるという ことはできず、これによって、原告の権利利益が日本国内で侵害され、又 は侵害されるおそれがあり、また、原告の権利利益について日本国内で損 害が生じたということはできない。
ウ 以上に対し、原告は、被告のウェブサイトに、被告が日本において97 件の商標登録出願をした旨や、被告が日本の顧客44名について商標登録 出願をした旨が記載されているところ、商標登録出願と契約書レビューサ ービスとの間では顧客層が重複することを主張し、証拠(甲34、35、 乙2)及び弁論の全趣旨によれば、被告のウェブサイト(https:/ /以下省略。 以下「legalforcel awウェブサイト」という。)には、「LegalForce RAPCは、 世界100カ国以上のクライアントを代理しています。」「米国以外では、 LegalForce RAPC Trademarkiaの上位出願国 は以下のとおりである。/(・・・中略・・・)日本 97/」「Lega lForce RAPCは、2009年以降、世界88カ国での商標出願 を支援している/(・・・中略・・・)日本」との記載が英語でされてい ること、被告が日本の顧客44名について商標登録出願をしたことが認め られる。
しかしながら、legalforcelawウェブサイトは本件被告ウ ェブサイト(https://以下省略) とドメイン名を異にするところ、原告の指摘するlegalforcelawウェ ブサイトの記載は、被告による商標登録出願やその代理についての記載で あると理解され、これらの記載をもって、本件被告ウェブサイトにおける 「AIに基づく契約書及び電子メールアカウントのレビュー」についての 被告標章(被告表示)の表\示が、日本の需要者を対象としたものであるこ との根拠とすることはできないし、本件被告ウェブサイトの表示により、\n原告の権利利益が日本国内で侵害され、又は侵害されるおそれがあること、 これらの権利利益について日本国内で損害が生じたと認めることもできな い。
さらに、原告は、原告の契約書レビューサービスと、被告の契約書レビ ューサービスとは、特に知的財産権に関する契約や英文契約について競合 するのであり、本件被告ウェブサイトの外観は本件原告ウェブサイトの外 観と酷似し、被告が悪意をもってこのような外観への変更をしたことによ り、日本の顧客が、原告が提供する契約書レビューサービスと被告が提供 する契約書レビューサービスを混同するおそれが高まっていること、原告 は外資系企業の顧客を有するところ、これら顧客は英語で記載されたウェブサイトを参照することを主張する。
しかしながら、本件被告ウェブサイトにおける「AIに基づく契約書及 び電子メールアカウントのレビュー」について、日本国内の利用者にサー ビスを提供していることを認めることができないのは前述のとおりである。 そして、本件原告ウェブサイトと本件被告ウェブサイトとを対比しても、 本件原告ウェブサイトは、日本語で記載され、その冒頭部分に「見落とし を無くそう、AIと。」とのキャッチコピー及び女性タレントの画像を掲載 するとともに、原告の商号及び日本における本店所在地を記載しているの に対し、本件被告ウェブサイトは、専ら英語で記載され、日本語での記載 はなく、本件原告ウェブサイトと同様のキャッチコピー又は画像は掲載し ておらず、被告の商号及び米国における本店所在地を記載しており、原告 の商号又は本店所在地を記載していないなど、これらウェブサイトの内容 は相違し、これらのウェブサイトが酷似しているということはできず、原 告の主張は当たらない。また、以上に述べたところに照らし、原告の主張 するその余の点も、上記判断を左右するには足りない。
エ 以上によれば、本件被告ウェブサイトにおける被告標章(被告表示)の\n表示により、原告各商標権又は原告表\示に係る権利利益が日本国内で侵害 され、又は侵害されるおそれがあり、また、原告の権利利益について日本 国内で損害が生じたとの客観的事実関係が証明されているということはで きない。そして、本件各証拠によっても、本件請求1から4まで、6の1 及び6の2に係る訴えについて、前記(1)ア及びイの客観的事実関係が証明 されているということはできない。
したがって、本件請求1から4まで、6の1及び6の2に係る訴えにつ いて、民訴法3条の3第8号に基づき、日本の裁判所が管轄権を有すると 認めることはできない。
(1) 事案に鑑み、民訴法3条の3第5号に基づく国際裁判管轄の有無に先立ち、 同第8号に基づく国際裁判管轄の有無について検討する。
ア 不法行為に基づく損害賠償請求訴訟につき、民訴法3条の3第8号の規 定に依拠して我が国の国際裁判管轄を肯定するためには、原則として、被 告が日本国内でした行為により原告の権利利益について損害が生じたか、 被告がした行為により原告の権利利益について日本国内で損害が生じたと の客観的事実関係が証明されれば足りると解するのが相当である(最高裁 平成12年(オ)第929号、同年(受)第780号同13年6月8日第 二小法廷判決・民集55巻4号727頁及び最高裁平成23年(受)第1 781号同26年4月24日第一小法廷判決・民集68巻4号329頁参 照)。
イ 民訴法3条の3第8号の「不法行為に関する訴え」は、違法行為により 権利利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者が提起する差止請求 に関する訴えをも含むものと解される。そして、このような差止請求に関 する訴えについては、違法行為により権利利益を侵害されるおそれがある にすぎない者も提起することができる以上は、同号の「不法行為があった 地」は、違法行為が行われるおそれのある地や、権利利益を侵害されるお それのある地をも含むものと解するのが相当である。 違法行為により権利利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者が提起する差止請求に関する訴えの場合において、同号の「不法行為があっ た地」が日本国内にあるというためには、被告が原告の権利利益を侵害す る行為を日本国内で行うおそれがあるか、原告の権利利益が日本国内で侵 害されるおそれがあるとの客観的事実関係が証明されれば足りるというべ きである(前記最高裁平成26年4月24日判決参照)。
ウ 以上を踏まえ、本件各請求に係る訴えについて、民訴法3条の3第8号 に基づき、日本の裁判所が管轄権を有するか否かを検討する。
(2) 本件請求1から4まで、6の1及び6の2に係る訴えについて
ア 原告は、被告が、本件被告ウェブサイトにおいて、契約書レビューサー ビスの提供に関する広告及び価格表に被告標章を付して電磁的方法により\n提供すること(本件請求1、2及び6の1)、契約書レビューサービスの提 供に被告表示を使用すること(本件請求3、4及び6の2)により、原告\nの権利利益が日本国内で侵害され、又は侵害されるおそれがあるとの客観 的事実関係が証明されている旨及び原告の権利利益について日本国内で損 害が生じたとの客観的事実関係が証明されている旨を主張する。
イ 前記前提事実(2)ウによれば、被告は、本件被告ウェブサイト上の「AI に基づく契約書及び電子メールアカウントのレビュー」についての広告及 び価格表に被告標章(被告表\示)を表示していたことが認められるところ、\n本件被告ウェブサイトは日本においても閲覧することができたものである (弁論の全趣旨)。 しかしながら、被告が、本件被告ウェブサイトにおける「AIに基づく 契約書及び電子メールアカウントのレビュー」について、日本国内の利用 者にサービスを提供していることを示す証拠は見当たらないところ、証拠 (甲2、8、乙1)によれば、1)本件被告ウェブサイトは全て英語で記載 されていること、2)本件被告ウェブサイトに掲載された価格表には、米国\nドルでの価格が表示されており、円での価格は表\示されていないこと、3) 本件被告ウェブサイトには、被告に対する問合せ先として、メールアドレ ス((メールアドレス省略))とともに米国の住所及び電話番号が記載されており、日本の住所又は電話番号は記載されていないこと、4)本件被告ウェブサイトには、日本語で作 成された契約書又は日本法を準拠法とする契約書に関するレビューサービ スについての記載はないこと、5)本件被告ウェブサイトのサーバは米国に 所在すること、6)被告は、「LegalForce」の文字を含む標章を付 した役務の提供を日本において申し出る計画を有していないことが認めら\nれる。以上の点を考慮すれば、本件被告ウェブサイトを日本において閲覧 することができたことを踏まえても、本件被告ウェブサイトにおける被告 標章(被告表示)の表\示が、日本の需要者を対象としたものであるという ことはできず、これによって、原告の権利利益が日本国内で侵害され、又 は侵害されるおそれがあり、また、原告の権利利益について日本国内で損 害が生じたということはできない。
ウ 以上に対し、原告は、被告のウェブサイトに、被告が日本において97 件の商標登録出願をした旨や、被告が日本の顧客44名について商標登録 出願をした旨が記載されているところ、商標登録出願と契約書レビューサ ービスとの間では顧客層が重複することを主張し、証拠(甲34、35、 乙2)及び弁論の全趣旨によれば、被告のウェブサイト(https:/ /以下省略。 以下「legalforcel awウェブサイト」という。)には、「LegalForce RAPCは、 世界100カ国以上のクライアントを代理しています。」「米国以外では、 LegalForce RAPC Trademarkiaの上位出願国 は以下のとおりである。/(・・・中略・・・)日本 97/」「Lega lForce RAPCは、2009年以降、世界88カ国での商標出願 を支援している/(・・・中略・・・)日本」との記載が英語でされてい ること、被告が日本の顧客44名について商標登録出願をしたことが認め られる。
しかしながら、legalforcelawウェブサイトは本件被告ウ ェブサイト(https://以下省略) とドメイン名を異にするところ、原告の指摘するlegalforcelawウェ ブサイトの記載は、被告による商標登録出願やその代理についての記載で あると理解され、これらの記載をもって、本件被告ウェブサイトにおける 「AIに基づく契約書及び電子メールアカウントのレビュー」についての 被告標章(被告表示)の表\示が、日本の需要者を対象としたものであるこ との根拠とすることはできないし、本件被告ウェブサイトの表示により、\n原告の権利利益が日本国内で侵害され、又は侵害されるおそれがあること、 これらの権利利益について日本国内で損害が生じたと認めることもできな い。
さらに、原告は、原告の契約書レビューサービスと、被告の契約書レビ ューサービスとは、特に知的財産権に関する契約や英文契約について競合 するのであり、本件被告ウェブサイトの外観は本件原告ウェブサイトの外 観と酷似し、被告が悪意をもってこのような外観への変更をしたことによ り、日本の顧客が、原告が提供する契約書レビューサービスと被告が提供 する契約書レビューサービスを混同するおそれが高まっていること、原告 は外資系企業の顧客を有するところ、これら顧客は英語で記載されたウェブサイトを参照することを主張する。
しかしながら、本件被告ウェブサイトにおける「AIに基づく契約書及 び電子メールアカウントのレビュー」について、日本国内の利用者にサー ビスを提供していることを認めることができないのは前述のとおりである。 そして、本件原告ウェブサイトと本件被告ウェブサイトとを対比しても、 本件原告ウェブサイトは、日本語で記載され、その冒頭部分に「見落とし を無くそう、AIと。」とのキャッチコピー及び女性タレントの画像を掲載 するとともに、原告の商号及び日本における本店所在地を記載しているの に対し、本件被告ウェブサイトは、専ら英語で記載され、日本語での記載 はなく、本件原告ウェブサイトと同様のキャッチコピー又は画像は掲載し ておらず、被告の商号及び米国における本店所在地を記載しており、原告 の商号又は本店所在地を記載していないなど、これらウェブサイトの内容 は相違し、これらのウェブサイトが酷似しているということはできず、原 告の主張は当たらない。また、以上に述べたところに照らし、原告の主張 するその余の点も、上記判断を左右するには足りない。
エ 以上によれば、本件被告ウェブサイトにおける被告標章(被告表示)の\n表示により、原告各商標権又は原告表\示に係る権利利益が日本国内で侵害 され、又は侵害されるおそれがあり、また、原告の権利利益について日本 国内で損害が生じたとの客観的事実関係が証明されているということはで きない。そして、本件各証拠によっても、本件請求1から4まで、6の1 及び6の2に係る訴えについて、前記(1)ア及びイの客観的事実関係が証明 されているということはできない。
したがって、本件請求1から4まで、6の1及び6の2に係る訴えにつ いて、民訴法3条の3第8号に基づき、日本の裁判所が管轄権を有すると 認めることはできない。
関連カテゴリー
>> 裁判管轄
>> 不正競争(その他)
>> ピックアップ対象
2025.01.14
令和4(ワ)8300 差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 令和6年10月10日 東京地方裁判所
不競法2条1項20号により、販売代理店として取得した同サービスに係る営業上の機密事項や営業手法を利用し、これと類似する事業を行うことが禁止されました。
ア 被告会社は、原告に対し、本件契約 3 条 2 項 4 号に基づき、「本サービスを …誤認されるサービスを行ってはならない」という競業避止義務を負う。また、本 件事業に関し、被告会社が原告との関係で代理商(会社法 16 条)の地位にあること は当事者間に争いがないところ、代理商は、許可なく「自己又は第三者のために会 社の事業の部類に属する取引をすること」を禁止されている(同法 17 条 1 項)。したがって、被告会社は、この観点からも、原告に対して競業避止義務を負う。
イ 前提事実及び前記各認定事実によれば、本件事業及びレキシル事業は、いず れも、広く採用活動を行う顧客から提供を受けた求職者等の履歴書や職務経歴書等 の情報を用いて、当該求職者等に係る WEB 調査及びその評価を行うサービスとい える。このため、レキシル事業は、本件事業と同種又は類似するサービスであり、 原告が事業として行う本件事業の部類に属する取引と認められる。なお、被告会社 は、レキシル事業として「レキシル」及び「レキシル+」を提供しており、それぞれ 別の商品として位置付けているとみられるものの、これらを併せた商品群を「レキ シル」と称して、一体的に宣伝広告活動等を行っていることがうかがわれることに 鑑みると、被告会社の原告に対する競業避止義務違反を考えるに当たっては、これ らの商品を区別して取り扱う必要はないというべきである。 また、本件提案書及び本件申込書とレキシル提案書及びレキシル申\込書の記載内 容の同一性又は類似性並びに本件契約締結及びその前後の経緯に鑑みると、被告会 社は、本件事業に関して原告から提供された資料に示された情報をもとにレキシル 提案書その他レキシル事業に関する資料等を作成し、レキシル事業に使用したもの と理解される。そうすると、被告会社は、原告に対する本件契約上の競業避止義務 にも違反したものといえる。
ウ これに対し、被告会社は、本件契約上の競業避止義務は代理商としての競業 避止義務よりも範囲を限定し、後者の適用を排除したものであり、また、仮に後者 が適用されるとしても、レキシル事業と本件事業とは内容や市場を異にすることな どを主張する。
しかし、上記のとおり、本件契約上の競業避止義務と代理商としての競業避止義 務とは内容を異にするところ、前者をもって後者の適用が排除されるとすべき理由 はない。また、本件事業とレキシル事業の内容や市場については、レキシル事業の うち「レキシル」は、本件事業とその内容及び市場を同じくすることは明らかとい ってよい。他方、「レキシル+」については、「第三者チェック」が実施されること もあって、「おすすめ対象」が中途採用者及び幹部社員採用候補者とされており、 その点では本件事業と異なる部分がある。もっとも、少なくとも中途採用者は「レ キシル」においても「おすすめ対象」とされており、また、幹部社員採用候補者に ついても WEB 調査が必要となる例のあることは容易に推察される。そうすると、 「レキシル+」を考慮に入れても、レキシル事業と本件事業とは、その内容及び市場 を共通にすると見るのが相当である。 その他被告会社が縷々主張する点を考慮しても、この点に関する被告会社の主張 は採用できない。
(3) 小括
以上より、被告会社は、レキシル事業の実施につき、原告に対する代理商として の競業避止義務(会社法 17 条 1 項 1 号)及び本件契約に基づく競業避止義務に違 反したものと認められる。
ア 被告会社は、原告に対し、本件契約 3 条 2 項 4 号に基づき、「本サービスを …誤認されるサービスを行ってはならない」という競業避止義務を負う。また、本 件事業に関し、被告会社が原告との関係で代理商(会社法 16 条)の地位にあること は当事者間に争いがないところ、代理商は、許可なく「自己又は第三者のために会 社の事業の部類に属する取引をすること」を禁止されている(同法 17 条 1 項)。したがって、被告会社は、この観点からも、原告に対して競業避止義務を負う。
イ 前提事実及び前記各認定事実によれば、本件事業及びレキシル事業は、いず れも、広く採用活動を行う顧客から提供を受けた求職者等の履歴書や職務経歴書等 の情報を用いて、当該求職者等に係る WEB 調査及びその評価を行うサービスとい える。このため、レキシル事業は、本件事業と同種又は類似するサービスであり、 原告が事業として行う本件事業の部類に属する取引と認められる。なお、被告会社 は、レキシル事業として「レキシル」及び「レキシル+」を提供しており、それぞれ 別の商品として位置付けているとみられるものの、これらを併せた商品群を「レキ シル」と称して、一体的に宣伝広告活動等を行っていることがうかがわれることに 鑑みると、被告会社の原告に対する競業避止義務違反を考えるに当たっては、これ らの商品を区別して取り扱う必要はないというべきである。 また、本件提案書及び本件申込書とレキシル提案書及びレキシル申\込書の記載内 容の同一性又は類似性並びに本件契約締結及びその前後の経緯に鑑みると、被告会 社は、本件事業に関して原告から提供された資料に示された情報をもとにレキシル 提案書その他レキシル事業に関する資料等を作成し、レキシル事業に使用したもの と理解される。そうすると、被告会社は、原告に対する本件契約上の競業避止義務 にも違反したものといえる。
ウ これに対し、被告会社は、本件契約上の競業避止義務は代理商としての競業 避止義務よりも範囲を限定し、後者の適用を排除したものであり、また、仮に後者 が適用されるとしても、レキシル事業と本件事業とは内容や市場を異にすることな どを主張する。
しかし、上記のとおり、本件契約上の競業避止義務と代理商としての競業避止義 務とは内容を異にするところ、前者をもって後者の適用が排除されるとすべき理由 はない。また、本件事業とレキシル事業の内容や市場については、レキシル事業の うち「レキシル」は、本件事業とその内容及び市場を同じくすることは明らかとい ってよい。他方、「レキシル+」については、「第三者チェック」が実施されること もあって、「おすすめ対象」が中途採用者及び幹部社員採用候補者とされており、 その点では本件事業と異なる部分がある。もっとも、少なくとも中途採用者は「レ キシル」においても「おすすめ対象」とされており、また、幹部社員採用候補者に ついても WEB 調査が必要となる例のあることは容易に推察される。そうすると、 「レキシル+」を考慮に入れても、レキシル事業と本件事業とは、その内容及び市場 を共通にすると見るのが相当である。 その他被告会社が縷々主張する点を考慮しても、この点に関する被告会社の主張 は採用できない。
(3) 小括
以上より、被告会社は、レキシル事業の実施につき、原告に対する代理商として の競業避止義務(会社法 17 条 1 項 1 号)及び本件契約に基づく競業避止義務に違 反したものと認められる。