|
|
ビ ジ ネ ス モ デ ル 特 許 の 基 礎
A Grounding in Business Method Patents
弁理士 古谷栄男
Hideo Furutani, Patent Attorney
ビジネスモデル特許の事例については、ビジネスモデル特許の流れを参照のこと。
ビジネスモデル特許とは何か?
(1)ビジネスモデル特許の定義
ビジネスモデル特許にいうとことろのビジネスモデルは、情報技術(IT)の分野において用いられているビジネスモデルとは必ずしも一致していないとの指摘がある。また、経営の分野では、ビジネスモデルは、儲けを生み出すビジネスの仕組みであるとしてとらえられているようである。一方、弁理士などの特許専門家の間では、ビジネス方法(Business Method)の特許と呼ばれ、ビジネスの仕組みや方法に関する特許としてとらえられてきた。
本稿では、ビジネスモデル特許を、ビジネスの仕組みや方法に関する特許であるとして話を進めたい。また、我が国では、この種の特許が話題となってから、一般に、ビジネスモデル特許と表現して報じられてきており、定着しつつあることから、ビジネスモデル特許という表現を用いることにした。
(2)ビジネスモデル特許の特徴
我が国において、ビジネスの方法そのものは、特許の対象とされていない。ただし、インターネットやコンピュータなどを用いたビジネス方法であれば、特許対象となり得る。
ビジネスモデル特許においては、ビジネスの方法や仕組みそのものに新しさがあり、ベースとなる技術には目新しさがない場合が多い。つまり、インターネットやコンピュータといったものを、どのように何に使ったのかという点に新しい部分が存する場合が多い。したがって、実質的にビジネスの仕組みそのものを権利内容としたに等しいというのが、ビジネスモデル特許の特徴である。
ビジネスモデル特許の歴史的背景
(歴史的な流れを説明していますので、お急ぎの方は「ビジネスモデル発明の特許性」からお読みください)
ビジネス方法に関連した特許は、1980年代から出願され、権利が取得されてきた。しかしながら、1998年ごろまでは、特許関係者の間ではともかく、広く社会的に話題となることは少なかった。1998年、米国のState Street Bank事件において、米国高等裁判所(CAFC)は、ビジネス方法も特許付与の対象となることを明確にした(その後、ビジネス方法自体は特許付与の対象ではないとする判決が出ている)。この判決が、2000年前後におけるビジネスモデル特許の流行をもたらしたきっかけとなった。
しかし、State Street Bank事件が1980年頃に出されたと仮定しても、やはり、ビジネスモデル特許がこれほど話題になるには、1990年代後半まで待たねばならなかったであろう。つまり、State Street Bank事件は、きっかけであって、そこには背景的な要因がある。
では、背景的要因とは何か? プロパテント政策とインターネットとの出会いである。つまり、①プロパテント政策に伴う、ソフトウエア関連発明に対する保護強化、②インターネットの爆発的な普及という2つの要因の相互作用によって、近年のビジネスモデル特許に対する注目の大きさが生じていると考える。
(1)ソフトウエア関連発明に対する保護強化(プロパテント)
1980年代に米国のレーガン政権が採ったプロパテント政策により、特許権の権利範囲の拡大、損害賠償額の高騰がもたらされた。プロパテント政策の初期において、日本のカメラメーカやゲームメーカが米国特許の侵害につき高額の損害賠償額を支払わされた事件もあった。いずれにしても、特許権者に対する強力が保護がもたらされることとなった。加えて、このプロパテント政策は、ソフトウエアに対する保護の拡大ももたらした。ソフトウエア特許を認めた1982年の米国最高裁Diehr判決、ソフトウエア特許の対象を明らかにした1987年の特許庁審査ガイドラインの改正、プログラムを記録した記録媒体を特許対象(法定の主題)として認めた1996年の審査ガイドラインの改正など、米国では、着実にソフトウエアに対する保護の拡大がなされてきた。
米国のプロパテント政策は、米国内における保護強化にとどまらず、TRIPSやWTOを活用して、他国に対して保護の強化も求めるものであった。日本やヨーロッパでも、このような流れを受けて、ソフトウエア関連発明の保護強化が図られるようになった。我が国では、1975年のコンピュータプログラムに関する発明の審査基準(その1)、1982年のマイクロコンピュータ運用指針、1993年のソフトウエア関連発明の審査基準と、ソフトウエア関連発明の保護範囲が拡大されてきた。特に、1997年のソフトウエア関連発明の審査運用指針では、米国に次いで、プログラムを記録した記録媒体を保護対象として認めた。ヨーロッパ特許庁も、IBM事件を契機に、記録媒体を認める方向を示しただけでなく、さらに進んで、プログラムそのものについても保護対象とする方向を示している。
以上のように、米国に端を発したプロパテント政策によるソフトウエア特許の保護強化は、日本、ヨーロッパにも波及している。
(2)インターネットの爆発的な普及
インターネット普及前においては、製品やサービスについての斬新なアイディアがあったとしても、それを事業化するには、製品の試作、販売チャネルの開拓等の手順を踏まねばならなかった。しかし、インターネットの普及によって、販売チャネルの開拓等が比較的容易となり、アイディアが事業に直結する可能性がもたらされた。たとえば、消費者の注目を売買する仕組みであるCyberGold社のAttention Brokerage特許(USP5794210)や、Buyer-drivenによってチケットなどの販売を仲介するプライスライン特許(USP5794207)は、インターネットというインフラがなければ、事業化が困難であったであろう。
アメリカに次いで、日本やヨーロッパでも、2000年頃にはインターネットが急激に普及した。したがって、それ以前なら、事業化が困難であり、また、事業化しても大きな市場を形成できないようなビジネスアイディアであっても、世界の顧客に直結したインターネットというインフラを前提として用いることにより、事業として実現することができる可能性が生じたのである。
(3)プロパテントとインターネットの出会い
以上のように、インターネットの発達により、ビジネスのアイディアが事業に直結する状況がもたらされるとともに、そのようなアイディアがプロパテント政策によってソフトウエア関連発明として強力に保護されるという2つの要因が生じた。このことが、ビジネスモデル特許に対する注目をもたらしていると思われる。
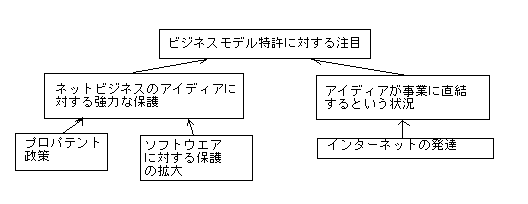
もちろん、ビジネスモデル特許は、インターネットに関連したものに限られてはいない。しかしながら、Open market社の電子取引3特許(USP 5,724,424:USP 5,715,314:USP 5,708,780)、Netcentives社の景品企画の特許(USP 5774870)、CyberGold社のAttention Brokerage特許(USP5794210)、プライスライン特許(USP5794207)、地図上の広告方法の特許(マピオン特許)(日本特許2756483)、Double Click社のウエブ上の広告方法特許(USP 5948061)、アマゾンドットコムの1クリック特許(USP 5960411)、WWWによるスケジュール管理の特許(USP 5960406)など、話題になった多くのビジネス特許がインターネットを用いたものである点に注目したい。
(4)ビジネスモデル特許の位置づけ
特許制度が企業活動にとって重要であることは、言い古されて来たことである。特許により、競争相手に対して優位に立つ。その意味において、特許を保有していることは、大きなメリットであった。しかし、それは、特定の企業を除いて、重要な事項のほんの一部にしかすぎなかった。研究開発部門、技術部門、知的財産部門の関係者だけが関与する事項だったのである。
しかし、2000年ごろになって、経済活動の中での特許制度の位置づけが、大きく変わったのである。コンピュータや通信(インターネット)の発達により、「知恵」そのものがビジネスになる時代になった。つまり、以前ならば、物やサービスの背後に隠れていた「知恵」が、ビジネスの最前線に登場したのである。このような「知恵」そのものがビジネスになる時代では、模倣されやすい「知恵」を保護する特許を活用しなければ、企業活動そのものが困難になることは明らかである。つまり、社会の大きな変革に対応して、社会全体が、特許制度を十分に活用し出したのである。2000年頃におけるビジネスモデル特許の盛り上がりは、このような流れが象徴的に現れたものである。
その後、ビジネスモデル特許のブームが去った後も、IoT、AI、ビックデータの発展や、物のサービス化といわれる大きな変化に伴って、ビジネスモデル特許が企業の特許戦略の中に着実に組み込まれていくこととなった。ビジネスモデル特許に関する特許出願件数も、2011年まで減少を続けたが、その後増加に転じている。2000年頃には8%と低迷していた特許査定率も、2015年頃には70%近くまで上昇している。
ビジネスモデル特許は、大企業による新規事業、既存事業の新展開の際だけでなく、起業の際の必須アイテムともいえる存在となっている。
ビジネスモデル発明の特許性
次に、日本において、どのようなビジネスモデルが特許されるのかについて説明する。一般に、特許を取得するためには、概ね以下の3つの要件を満足しなければならない。
i)発明であること
ii)新規性があること
iii)進歩性があること
これらの要件のうち一つでも欠いている場合には、特許を取得することはできない。したがって、たとえ、斬新なアイディアであっても、そのアイディアが発明に該当しないと認定されれば、特許権は与えられないことになる。
(1)発明であること
特許法は、発明を保護するために発明に対して特許権を与えるものであるから、「発明」でないものに特許を付与しないのは当然である。多くの技術分野においては、そのアイディアが「発明」であるか否かが問題となるケースは少ない。しかし、ビジネスモデル関連発明をはじめとするソフトウエア関連発明においては、それが「発明」に該当するか否かが問題となることが少なくない。
特許法第2条では発明を定義している。「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを言うとしている。これを受けて、特許庁では、審査基準を公表し、ソフトウエア関連発明について、どのようなものが自然法則を利用した技術的思想の創作に当たり、どのようなものが自然法則を利用した技術的思想の創作に当たらないのかを示している。ビジネスモデル発明もソフトウエア関連発明の一形態と考えられるので、この審査基準の考え方が審査において適用される。
この審査基準では、自然法則以外の法則のみを利用したアイディアは、発明に該当しないとしている。たとえば、以下に示すような、航空券の販売仲介方法は、経済法則のみを利用したものであるとして、発明ではないとされることにろう。
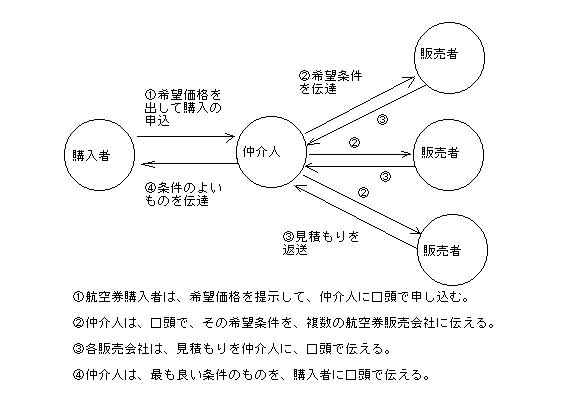
上記のように、ビジネス方法、ビジネスの仕組みそのものは、「発明」ではないとして、新規性、進歩性の判断をするまでもなく、特許が与えられないことになる。
しかしながら、審査基準においては、上記のようなビジネスの方法であっても、コンピュータを用いることを前提としている場合には、「発明」であるとして特許対象になりうる旨を述べている。したがって、インターネットを用いたビジネスモデルは、特許対象となりうる。
なお、審査基準では、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)又はその動作方法が構築されていれば、「発明」に該当するとしている。
したがって、下記に示すような、インターネットを用いた航空券の販売仲介方法は、発明であるとして特許対象となりうる。
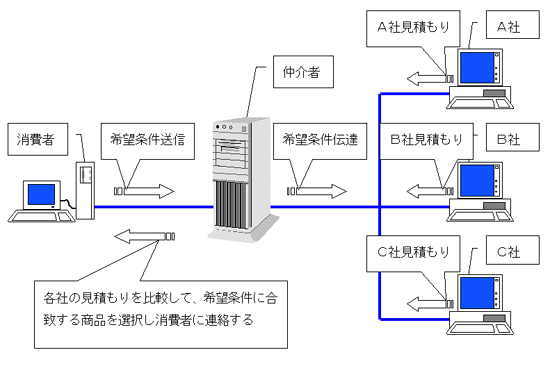
(出典特許庁)
(2)新規性があること
発明であることを前提として、特許を取得するためには「新規性」が要求される。つまり、特許出願より前に、そのインターネットを用いたビジネスモデルが知られていた場合には、新規性がないとして特許を取得することができない。なお、発明したもの自身が出願前に発表を行って、その内容を公知にした場合であっても、新規性がないとされるので注意が必要である。
特許法29条では、以下に該当するものは新規性がないと規定している。
・特許出願前に日本国内において公然知られた発明(特許法29条1項1号)
・特許出願前に日本国内において公然実施された発明(同2号)
・特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(同3号)
なお、出願者自身が発表して新規性を失った場合には、1年以内に出願することにより、新規性を失わなかったものとする例外的な取り扱いもある(30条)。しかし、この規定に頼りすぎることは危険であり、原則として、発表前に出願を済ませておくことが好ましい。
(3)進歩性があること
特許権取得のためには、「発明」であり「新規性」があるだけでなく、「進歩性」が要求される。進歩性とは、当該分野の専門家が容易に思いつかない程度を言う。
たとえば、ビジネスモデルそのものは既に公知であっても、これをインターネットを用いたビジネスモデルとして出願すれば、新規性はある。しかし、単にインターネットを用いて実現したというだけであれば、進歩性がなく、特許は付与されない。審査基準においても、人間の行為として既に公知のものを、単にコンピュータを用いて行ったと言うだけでは、進歩性はないと説明されている。
ただし、インターネットを用いてビジネスモデルを運用する際に、何らかの工夫がなされていれば、進歩性があると主張できる可能性が生じる。また、ビジネスモデルそのものが新しければ、進歩性を主張できる可能性がある。
進歩性についての解説(動画)
進歩性についての解説(文章)
アメリカ・ヨーロッパにおけるビジネスモデル発明の特許性
以上、日本での特許性について説明したが、主要国であるアメリカ、ヨーロッパでの特許性、特に発明であることという要件について説明する。
①アメリカ
アメリカでは、1998年のState Street Bank事件判決によって、コンピュータを用いない純粋なビジネス方法に対しても特許付与が認められるようになった。世界で最も広くビジネス方法を特許対象として認める国となった。しかし、2014年のAlice判決により、ビジネス方法自体は抽象的なアイディアであって特許対象ではないとされ、しかも、それをコンピュータシステムによって実現したというだけでは、依然として特許対象ではないとされることになった(101条拒絶)。その結果、アメリカにおけるビジネスモデル特許取得は、日本よりもはるかに厳しいものとなった。
しかし、2020年現在、ビジネス方法に対する米国特許庁の運用がかなり緩やかになってきており、101条によって特許対象で無いとして拒絶される割合は減少している。
米国特許庁のビジネス方法特許に関するサイト
②ヨーロッパ
ヨーロッパ特許庁においては、従来技術に対し、特許性が排除されていない分野における技術的貢献がなければ保護対象とならない(ヨーロッパ特許審査ガイドラインC-IV 2.1~2.2参照)。したがって、これを厳格に運用すると、ビジネス方法にのみ新しさがある場合には、発明でないと認定される。日米欧3極の中では、ビジネスモデル特許の取得が最も困難である。
その他
ビジネスモデル特許の事例については、ビジネスモデル特許の流れを参照のこと。
ソフトウエア特許については、ソフトウエア特許の基礎を参照のこと。
AI特許については、AI特許の取得と活用を参照のこと。
以上
NOTES
(C)2020 Hideo FURUTANI / furutani@furutani.co.jp
MAIL TO
furutani@furutani.co.jp
ビジネスモデル特許の目次へ
発表論文・資料集の目次へ
トップページ(知的財産用語辞典)へ
|